ravideの食育=食表現『食を通したヒト・モノ・コトとの対話』
前回『食べずにはいられない、食欲をそそる「中動態」的提案』はこちらからご覧ください。
さて、前回は食べることは表現の一つでしかない、食を通して子どもたちが表す全てを尊重することが「食表現」であり、その過程が尊重されてこそ、表現の一つとして、自ら「思わずひとくち」が表れることを述べてきました。今回はさらに「食表現」の内容を深掘りしていきましょう。

食を通したヒト・モノ・コトとの対話
前回の最後にも少し触れましたが、食表現の目的は、食に関する単なる知識伝達でも、クッキング活動的に料理をつくることでもありません。食表現の目的は「食を通したヒト・モノ・コトとの対話」なのです。
「食表現の概念」を分かりやすくするために、保育園・幼稚園の先生たちに親しみのある「造形遊び」を例に考えてみましょう。ここでは、「制作遊び」と「造形表現」の対比によって考察してみます。
いわゆる「制作遊び」では「作るもの」から発想することが多いのではないでしょうか。「何を作るか」が決まっている活動には自然と「枠組み」が生まれます。どんなに一人ひとりの表現を尊重しようとしても、「何かをつくること」が目的となる提案である限り、大人が用意した「何か」が前提となり、それ以外の表現は「枠から外れたもの」として捉えられてしまいます。
そんな活動の中では、どんなに一人ひとりの表現を尊重しようとする思考や姿勢があったとしても、活動の前提が「何かをつくること(それを経験すること)」である以上、大人の提案と異なる表現をした子どもへ向けられるまなざしは、「良い意味で枠から外れたもの」と受け止めるにとどまるのではないでしょうか。反対に、子どもたちの多くは自由に使える画材や廃材、道具と空間、をして時間と自由が尊重されていれば、大人に課せられずとも「自分の好きなものを制作して遊ぶこと」をはじめるものです。保育園・幼稚園は、これまで積み重ねてきた経験や「月一制作」のような枠組みは一度手放し、新しい視点を取り入れ、問い直すことが大切なのです。
では制作遊びではなく「造形表現」とはどんな提案なのか、見ていきましょう。
○ravide的に考える「造形表現」の提案
①「何を作るか」ではなく、「子どもの興味・関心や発達をもとに、どんな技法や素材に親しめると表現が広がり、深まるか」という問いから提案を考える。
②その素材や技法を用いながら、アイメッセージとして「先生はこんなふうに表現してみたよ(こんなものをつくってみたよ)」と示す。
この①と②によって、
・「何かを作る」という枠組みを取り払うことができます
・一人ひとりの本質的な表現が自然に生まれ、それを尊重できるようになります
・活動に枠を設けないため、「枠から外れる」といった評価が不要になります
・同じ素材や技法を使っても、その子自身ならではの表現を見守ることができます
このように、何か作るものを固定化してしまう「制作遊び」的な提案ではなく、一人一人が素材や技法との対話を通して表現することを尊重する「造形表現」という提案によって前提が変わることで、子どもの表現のあらわれ、大人の表現の見方は大きく変わってきます。
「作るものを決める→素材や技法を考案する→実践する→枠内に収まるか、枠を越えるかを評価する」という従来の思考の流れを問い直すと、以下のような新しい提案のプロセスが見えてきます。
○ravide的提案:造形表現のプロセス
・造形表現の思考
↓
・ものごととの対話を尊重する営み
↓
・子どもの姿(思い・願い・興味・関心・好奇心)
↓
・表現を広げ、深めるための素材・技法
↓
・「先生はこんなふうにしてみたよ」という『実践的アイメッセージ=提案』
↓
・素材・技法・提案に触発されながら、その子自身の表現が自然に表れ、生じる
制作遊びではなく、あえて「造形表現」という言葉を用いて考察することで、表現について深めてきました。(さらに深めていくと、制作遊びと造形表現の線引きそのものが意味を持たなくなり、造形表現の時間だから表現するのではなく、日常の中に自然と「造形表現」が息づき、すべては「遊び」となるかもしれませんが。)
話を「ravideの食育=食表現」へ戻します。
ravideの食育=食表現では、制作遊びでいう「何かをつくること」、食育でいう「何かを食べること」という「結果」を求めません。「結果」を求めるために遊びを提案するのではないのです。そもそも、大人が求める何かへ向かうための活動である時点で、それは「遊び」ではなく「課題」であり、もはやそれは「保育」でも、「幼児教育」でもない「なにか」になっています。
では食表現では何をするのか?造形表現における、素材を「食材」に、技法を「調理方法」に置き換えてみると明確になってきます。子どもたちが十分に食材と触れ合い、観察する機会と時間をつくること。調理過程の一つ一つを、料理を作ることを目的とした単なる「作業工程」にしてしまうのではなく、子どもたちが調理過程そのものと対話する「調理科学の不思議さ」に気づき味わえるような問いかけをし、対話と思考する機会を持つこと。子どもたち自身で手を動かし、感覚を働かせる機会と時間を十分に持つこと。それらを通して、一人一人の興味関心ごとによって「食への親しみ・楽しみ」を広げ、深め、感じたこと試行したことを表現し合うことです。一見すると同じ提案の中で、同じ活動をしているのだけれど、そこで表れる表現は一人一人異なっている。まさに「造形表現」と同じような営みを大切にします。

調理過程では、量を測ることや人数分に切ったり分けたりすること、買い出しでお金を計算して支払いをすることなどから「数に親しむ機会」、食材や生産地の名前から「文字に親しむ機会」も提案します。食材の端材や皮を使って造形遊びをすることも…

そして何より、チームになって使う食材や調味料について相談すること、あえて複数の色の生地から一人一色ずつ配ることで、他の色を使いたい時は友だちと交渉して交換すること、自分の盛り付けを紹介しあったり、共食の中で感じたことを伝えあったりすること、料理の役割分担を話し合うことなど「人と対話する機会」を提案していきます。
それら様々な提案を通して、子どもたちは豊かな表現を見せてくれるのです。ここまでの内容を理解できれば食育において「食べる食べない」といった結果は大したことではなく、食を通して様々な表現に触れることで多方面への育ちの機会があることがわかってくると思います。
そして、こうした遊びの中で「思わずひとくち」を食べている子どもたちの姿を、私たちは本当に数多く見てきています。
最近では「(発達が)気になる子」が増えていると聞きます。そんな「気になる」の中には「偏食」の相談も多いようです。私たちも「発達支援」や「感覚統合」の観点から学びを深めている中で出会った本の内容に、まさにravideの提案とリンクするものを見つけたので以下に抜粋してご紹介します。
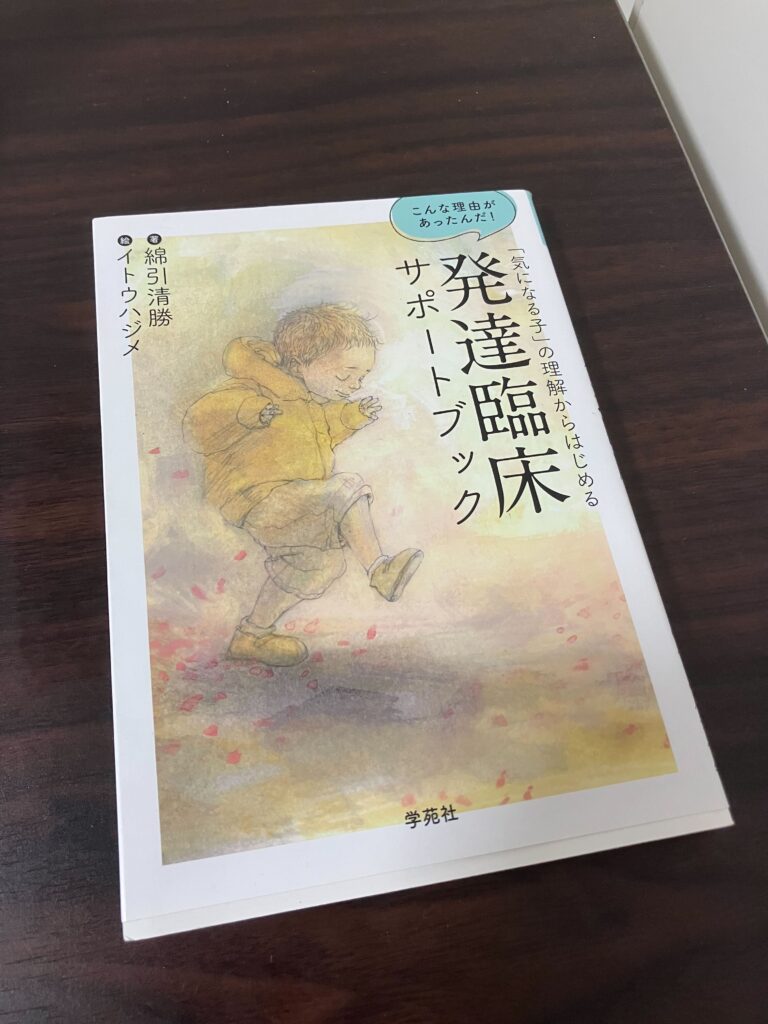
「ー偏食が強い子の支援ー
乳幼児期は、身体の発育という視点からも、バランスの良い栄養を摂らせたいと考えることは、当然のことです。ただし、食事というのは単なる栄養摂取のためだけのものではなく、それ自体を楽しめるようにしていくことが、ひいては豊かな生活につながっていきます。その点を考慮すると、無理して食べることがゴールではなく、食べることに楽しみを感じ、様々な食材に関心がもてるようにな ることが重要だといえます。そのためには、最初から咀嚼をして飲み込むことを目標とするのでは なく、次のようなステップが考えられます。
①食べ物を観察する
②食べ物の匂いを嗅ぐ
③食べ物の味を確かめる
④食べ物を少しだけかじってみる
⑤ 食べ物を少しだけ口の中に入れて咀嚼する
偏食が強い子にとっては、この五つのプロセスだけでも、自分にとって害のないものだと安心できるためには、他の子どもたちよりも時間がかかることがあります。その点では、ここで焦ったり、急かしたりすると逆効果になるため、のんびりと腰を据えてチャレンジしていく姿勢が大事になります。 そうすることで、昨日まではできなかったことがちょっとずつできるようになっていく成功体験を積み重ねていくことができます。
『「気になる子」の理解からはじめる発達臨床サポートブック 出版:学苑社 著者:綿引清勝』より抜粋」
ravideでは、こうした視点から「食」をきっかけに様々なことへ興味関心を持ち、感じたことや思考したことを表現し合うことを通して、多方面へ育っていくような食育=「食表現」を提案しています。「食べる」かどうかは子ども自身が決めることであり、それは「表現」の一つでしかないのです。
まずは「好き嫌いなく食べて欲しい」という大人のエゴを捨てて、「好き嫌いなくなんでも食べられること=良いこと」という固定観念をほぐして、本当の意味で子どもと一緒に「食を楽しむこと」をしてみましょう。そうして子どもと共に、真に食を楽しむ経験を分かち合うことでこそ、自然な「表れ」として偏食が和らいでいくものです。
今だけravideの食育=食表現を1回、無料で試すことができます!実践園の見学も随時受け付けています!ぜひお気軽にお問い合わせください。
