ravideの食育=食表現『食表現とは③』
前回②部『②食を通したヒト・モノ・コトとの対話』はこちらからご覧ください。
ravideが提案する「食育=食表現」について少しずつ輪郭が見えてきたでしょうか?第③部では、食表現の「食を遊ぶ」ということについて、考えてみます。
③食表現=食を遊ぶ:脱「食育=栄養士が行う授業・単発イベント」
○遊びとは「主体・創造、探究・協働」的な営み
「食を遊ぶ」と聞くと、みなさんはどんなことを思い浮かべるでしょうか?もしかすると「下品」な、食事のマナーに反するような様子を想像した人も少なくないと思います。ravideの提案をしてきた園でも、はじめは「食を遊ぶ」という言葉に抵抗感を持つ人に出会ってきました。しかし、その感覚や固定観念こそ、今の「食育の課題」を物語っています。
子どもたちは「生活と遊び」を通して「主体的に活動し」、自ら育っていくということが、各指針や要領に示されているにもかかわらず「食育」だけが、一斉・一方通行型の知識伝達やクッキングを主としたいわゆる「授業形式」的な営みになってしまっているのです。「遊び」になっていないのです。自由がなければ「主体性」はありえません、主体性がなければ「遊び」とは言えません。「遊び」になっていない、大人から課せられた「何か」から、子どもたちは健やかな育ちは望めません。
また、栄養士、保育士が日常業務に追われている背景もあり、食育が「単発的なイベント」になってしまい「生活や遊び」に含まれる「継続性・連続性」に欠ける取り組みになっていることも多いのです。それでは、一時的な楽しみはあったとしても、「子どもの発達につながる」活動にはなっていきません。本来、「生活と結びつく、遊びとしての営み」でなければ、子どもたちが「食を通して育っていくこと」は叶わず、「食育」とは呼べないのだと考えています。
だからこそ、抵抗感を持つ人が多くいることを承知で、私たちは「食育=食表現=食を遊ぶこと」を伝えいます。

ravideの食表現では、「食を遊ぶ」ことを提案の中で徹底しています。それは「遊び」こそ学びや育ちにつながる営みであり、遊びには「遊びそのものに人生を豊かにする価値」があるものと考えているからです。そこでキーワードとなるのが「主体・創造・探究・協働」です。これらの要素を持つ営みを、私たちは「遊び」と呼んでいます。「食」を通してこうした体験を子どもたちに提案していくのが「食表現」なのです。
そう考えた時、皆さんが最初に「食を遊ぶ」という言葉から連想した子どもたちの姿も、実は否定できない姿にも見えてくるのです。まさに、乳児の離乳食でいう「遊び食べ」です。
食材を手で触り目で確かめる、コップのお茶の中に入れ変化を観察する、食材・食具を机の下に落としてみる…それらの行為は、ある意味大人に言われてしているでもない「主体的」な姿なのです。目の前の素材の変化を「創造」し、どこまでも「探究」しているとも見えます。そして、だからといってそれを「全てよし」としましょうと、言っているのではありません。
子どもは食材だけでなく、人とも対話しているのです。自分が示した表現(行為)によって食材がどのように変化するのかを観察するのと同様に、自分の表現に対して「人」がどのような反応を示すのかをよく観察し感じ取っています。そうした関わり合いによって、「人間関係」や「社会性(文化)」を学んでいきます。子どもの表現に大人が応じること、また一人の子どもの表現に触発されて子どもたちが表現を分かち合うこと(例えば、乳児の一人がスプーンで食器に触れると音が鳴ることを発見すると、友だちも真似をするような様子があったりします)、そうした関係性は「協働」的な営みといえます。「乳児の遊び食べ」の中にも多くの学びと育ちがあるのです。
そうとはいえ、大人は「食事の時間」「それは玩具じゃなくて食べ物です」ということに縛られてしまいます。子どもの遊び食べに対して、つい否定的な関わりをしてしまうものです。
当たり前のことですが、子どもの食環境は、大人の影響を大きく受けていることに自覚的になることは非常に重要なことです。胎児期、乳児期から親の体とつながり食べたものを通して栄養をもらい、離乳食以降も大人が用意した「環境」で(子どもに食べさせるもの以上に、どのように食べるか、大人が何を食べているのかも大切)、用意されたものを食べるほか生き延びる術はないのです。それでは子どもたちはいつ、「自ら食への興味関心」を深めればよいのでしょうか。提供され続けてばかりいるから、「食」へ対する「主体性」を失い、受け身になり「これは嫌だあれは良い」となる面もあるのではないでしょうか。
「子どもたちに食事に関心を持ってほしい」「偏食なくなんでも食べてほしい」そう願いながら、「遊び食べ」にはじまる、子どもたちが自ら「食への親しみを深めよう」とする姿勢を否定してしまう…。
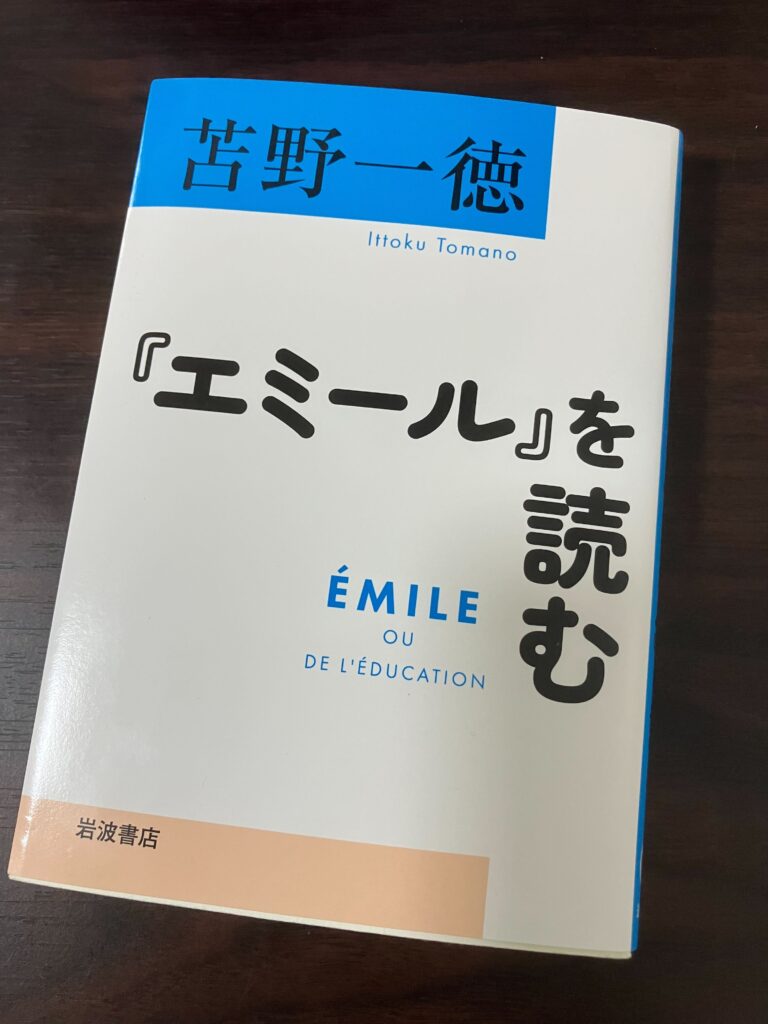
「あれしなさい、これしなさい、あれするな、これするな。そんなことばかり言い続けていたら、その子はそのうち『息をしなさい』と言わないと呼吸さえしなくなるぞ。
『エミールを読む』出版:岩波書店 著者:苫野一徳 より抜粋」
教育哲学においては、ルソーによって260年も前からこうしたことが謳われているのです。あえて極端な言い方をしますが、子どもたちが自ら食事への興味を自ら深めようとして行っている行為を「遊び食べ」と称されて大人に制止され、それでいながら食材そのもののことも、調理過程も知る機会を与えられず、大人からしたら「料理」でも、子どもからすると「得体の知れないもの」を目の前に置かれて、食べることを課される…ルソーの言わんとすることは、現代の子どもたちの「食事環境」においても同様なのではないかと思ってしまいます。
ちなみに余談ですが、熊本大学の苫野一徳先生が掲げる教育の「個別化・協働化・プロジェクト化」は、まさにravideの提案にも通ずる理論であり、私たちも今後、学校教育への参画も検討している中で、ブログでもその内容について触れていきたいと考えています。経済産業省が出しているこちらの資料が分かりやすいのでご参照ください。
話を戻します。
ravideは乳児期から、子どもたちが主体的に「食」へ親しめる提案をしています。ある意味、大人が納得感を持って、子どもたちは自由で主体的に「遊び食べ」ができる機会のデザインなのかなと考えています。子どもたちが、食材や調理方法へ「自ら」親しみ、創造・探究的に対話し、周囲の大人や友だちと影響し合いながら「食べるかどうか」を「自己決定する」そんな活動内容です。
・地産地消が薄れ生産地との距離が生まれたこと
・各家庭で栽培をする機会が減ったこと
・安全面への配慮として子どもたちが台所に入る機会が無くなったこと
・食事の利便性が高まることで「調理過程に親しむ機会」が大きく減少していること
・家族やコミュニティで食卓を囲む機会が失われつつあること
こうしたさまざまな社会的な背景によって、子どもたちが「食へ親しむ機会が損なわれている」現代だからこそ、必要な取り組みだと考えています。そして、子どもの発達面だけでなく、そうした子どもたちの原体験の機会損失によって、結果的に「偏食」が増えていることも考えられます。

ravideでは、保育・教育観を磨いた料理人が保育園の中に入ることで、「食を遊ぶ=食表現」という「感動体験」を届ける提案をしています。それは「授業」ではなく、「遊び」なのです。1歳児でも、気づけば30分以上椅子に座って、食材や調理方法と向き合い、「食に関するコト=食事」を夢中で「味わう」姿も珍しくありません。
今だけravideの食育=食表現を1回、無料で試すことができます!実践園の見学も随時受け付けています!ぜひお気軽にお問い合わせください。
